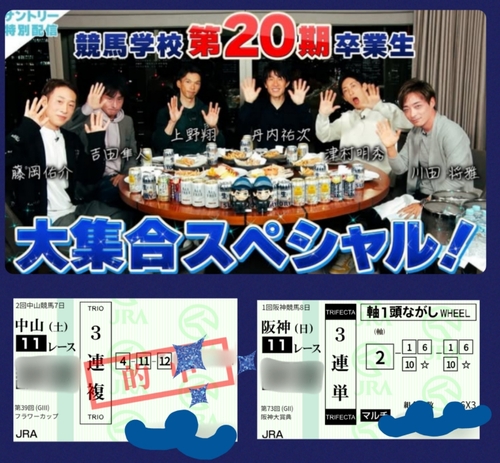べらぼう途中感想(1〜11話)

こんばんは。浮世絵大好きおばさんです🌊
推し浮世絵師は歌川国芳!
以前、秋田県立近代美術館にて、国芳の企画展が開催された時は、もちろん観に行きましたともさ。
金魚づくしシリーズに、東海道五十三疋に、相馬の古内裏。200年以上の時を越えて、肉眼で対峙することができた推しの作品に、私の心の中の辻仁成が「やっと会えたね」と呟きましたともさ。
ワタクシがなぜ、浮世絵を含む化政文化を愛するのか。
それは「化政文化って、めっちゃパンクだから」です。
質素倹約を推奨し、学問を朱子学のみに制限し、出版物を取り締まり、庶民を厳しく押さえつけていた寛政の改革。
その反動から、庶民たちの間で社会風刺を混じえたアート・ムーブメントが興りました。
それが化政文化です。
元禄文化が、上流階級の特権としてのお芸術(おっと、琳派の悪口はそこまでだ)であったのに対し、化政文化は、町民たちのDIY精神から生まれたカウンターカルチャーです。
表現の自由、知性感性の選択を規制弾圧しようとする体制への反骨心。それを武力、暴力ではなく、美の力、芸の力によって表現した。
これはまさに、精神性においてはパンク・ロックなのです。
・
・
・
歴史好き・大河好きの仲良しさまに「今度の大河は浮世絵がテーマです」と教えて頂いて見始めた「べらぼう」。
浮世絵師オールスターズはまだ出てきていないけど、毎回感激しながら鑑賞しています。
既婚者女性の化粧方法の時代考証が正確だったり、衣紋の抜き方がちゃんと女郎風だったり、蕎麦の食べ方がちゃんと江戸っ子式だったり、さすがは天下のNHK。細部にまで、ちゃんと江戸風俗のセオリーを行き渡らせていて惚れ惚れします。
特筆すべきは主人公・蔦重の幼なじみであり花魁の瀬川を演じる小芝風花さん。本当に素晴らしかった。演技を越えて、全身全霊で江戸の粋を体現して下さっていたと思います。
瀬川も11話にて身請けされ、一旦、吉原からは退場、蔦重も少年期の恋に別れを告げ……と、物語としての第一部が終わり、一区切りついたところで、ここまでの感想をば。
・
・
・
「べらぼう」における花街文化の描き方について「苦界を華やかで煌びやかなものとして美化するのは良くない」との批判も出ていたようですが、まず、芸術と社会道徳の成熟度って比例しないし、作者の境遇の良さと、生まれる作品の良さも比例しないのですよ。
化政文化が、表現の自由の圧迫に対する反動として狂い咲いたように、苦しみや哀しみや憤りから生まれる芸術にしか宿らない豊かさ、毒毒しさ、華々しさ、ってぇもんがある。
世の中が荒んでいるからこそ、個人の境遇が地獄じみているからこそ、産み落とされる芸術があるのです。
ドストエフスキーだって
😨銃殺刑をすんでのところで免れる
↓
😨シベリアに流刑
↓
😨服役生活
がなければ、世界的文豪になってはいなかったと思うよ。
更に。人間が生きていくのに、文化芸術は必要ありませんが、人間が人間らしく生きていくのには、文化芸術が必要です。
「べらぼう」とは何を描きたいドラマなのか。
「苦界を美化している」「公娼制度を肯定している」のではなく、苦しいことが多い世界だからこそ、美しいものが必要だった。美しいものに触れる機会、美しいものを作る機会を増やすシステムを普及させることが必要だった。
人間性を失わないために。
それを誰より理解し、吉原における文化芸術啓蒙活動を牽引したのが蔦屋重三郎という人間だった、という話なのではないでしょうか。
本作では、蔦重が遊女たちに貸本を届けにくるシーンが幾度も挟まれます。人が苦界の中で夢を見る手段が読書であり、教養という武器を得る手段も読書であった、ということを暗に示しているように感じます。
さらに、吉原を文化水準の高い場所にプロデュースすることができれば、客筋も良くなり、女郎たちの労働環境の向上にも繋がる、と蔦重がプレゼンする場面もありましたね。
美化肯定するどころか、吉原のあり方、女郎たちの置かれた現状を良しとしないからこそ、現実を直視し、孤軍奮闘し始めたのが、蔦屋重三郎という人だったわけで。
蔦重は後に、葛飾北斎や喜多川歌麿、東洲斎写楽ら、名だたる浮世絵師たちを見出し、パトロネージュし、浮世絵の普及発展にも尽力することになります。
沢尻エリカの元旦那の肩書が「ハイパーマルチメディアクリエイター」だったのを受け、当時、多くの日本人は「え……胡散が臭い……」と感じたことでございましょうが、蔦屋重三郎こそが、化政文化をプロデュースしたハイパーマルチメディアクリエイターの名にふさわしい人物なのですよ。
・
・
・
唐丸少年は喜多川歌麿になって再登場する、に500ペリカ。
推し浮世絵師は歌川国芳!
以前、秋田県立近代美術館にて、国芳の企画展が開催された時は、もちろん観に行きましたともさ。
金魚づくしシリーズに、東海道五十三疋に、相馬の古内裏。200年以上の時を越えて、肉眼で対峙することができた推しの作品に、私の心の中の辻仁成が「やっと会えたね」と呟きましたともさ。
ワタクシがなぜ、浮世絵を含む化政文化を愛するのか。
それは「化政文化って、めっちゃパンクだから」です。
質素倹約を推奨し、学問を朱子学のみに制限し、出版物を取り締まり、庶民を厳しく押さえつけていた寛政の改革。
その反動から、庶民たちの間で社会風刺を混じえたアート・ムーブメントが興りました。
それが化政文化です。
元禄文化が、上流階級の特権としてのお芸術(おっと、琳派の悪口はそこまでだ)であったのに対し、化政文化は、町民たちのDIY精神から生まれたカウンターカルチャーです。
表現の自由、知性感性の選択を規制弾圧しようとする体制への反骨心。それを武力、暴力ではなく、美の力、芸の力によって表現した。
これはまさに、精神性においてはパンク・ロックなのです。
・
・
・
歴史好き・大河好きの仲良しさまに「今度の大河は浮世絵がテーマです」と教えて頂いて見始めた「べらぼう」。
浮世絵師オールスターズはまだ出てきていないけど、毎回感激しながら鑑賞しています。
既婚者女性の化粧方法の時代考証が正確だったり、衣紋の抜き方がちゃんと女郎風だったり、蕎麦の食べ方がちゃんと江戸っ子式だったり、さすがは天下のNHK。細部にまで、ちゃんと江戸風俗のセオリーを行き渡らせていて惚れ惚れします。
特筆すべきは主人公・蔦重の幼なじみであり花魁の瀬川を演じる小芝風花さん。本当に素晴らしかった。演技を越えて、全身全霊で江戸の粋を体現して下さっていたと思います。
瀬川も11話にて身請けされ、一旦、吉原からは退場、蔦重も少年期の恋に別れを告げ……と、物語としての第一部が終わり、一区切りついたところで、ここまでの感想をば。
・
・
・
「べらぼう」における花街文化の描き方について「苦界を華やかで煌びやかなものとして美化するのは良くない」との批判も出ていたようですが、まず、芸術と社会道徳の成熟度って比例しないし、作者の境遇の良さと、生まれる作品の良さも比例しないのですよ。
化政文化が、表現の自由の圧迫に対する反動として狂い咲いたように、苦しみや哀しみや憤りから生まれる芸術にしか宿らない豊かさ、毒毒しさ、華々しさ、ってぇもんがある。
世の中が荒んでいるからこそ、個人の境遇が地獄じみているからこそ、産み落とされる芸術があるのです。
ドストエフスキーだって
😨銃殺刑をすんでのところで免れる
↓
😨シベリアに流刑
↓
😨服役生活
がなければ、世界的文豪になってはいなかったと思うよ。
更に。人間が生きていくのに、文化芸術は必要ありませんが、人間が人間らしく生きていくのには、文化芸術が必要です。
「べらぼう」とは何を描きたいドラマなのか。
「苦界を美化している」「公娼制度を肯定している」のではなく、苦しいことが多い世界だからこそ、美しいものが必要だった。美しいものに触れる機会、美しいものを作る機会を増やすシステムを普及させることが必要だった。
人間性を失わないために。
それを誰より理解し、吉原における文化芸術啓蒙活動を牽引したのが蔦屋重三郎という人間だった、という話なのではないでしょうか。
本作では、蔦重が遊女たちに貸本を届けにくるシーンが幾度も挟まれます。人が苦界の中で夢を見る手段が読書であり、教養という武器を得る手段も読書であった、ということを暗に示しているように感じます。
さらに、吉原を文化水準の高い場所にプロデュースすることができれば、客筋も良くなり、女郎たちの労働環境の向上にも繋がる、と蔦重がプレゼンする場面もありましたね。
美化肯定するどころか、吉原のあり方、女郎たちの置かれた現状を良しとしないからこそ、現実を直視し、孤軍奮闘し始めたのが、蔦屋重三郎という人だったわけで。
蔦重は後に、葛飾北斎や喜多川歌麿、東洲斎写楽ら、名だたる浮世絵師たちを見出し、パトロネージュし、浮世絵の普及発展にも尽力することになります。
沢尻エリカの元旦那の肩書が「ハイパーマルチメディアクリエイター」だったのを受け、当時、多くの日本人は「え……胡散が臭い……」と感じたことでございましょうが、蔦屋重三郎こそが、化政文化をプロデュースしたハイパーマルチメディアクリエイターの名にふさわしい人物なのですよ。
・
・
・
唐丸少年は喜多川歌麿になって再登場する、に500ペリカ。